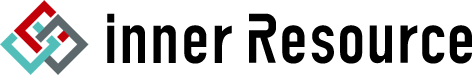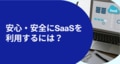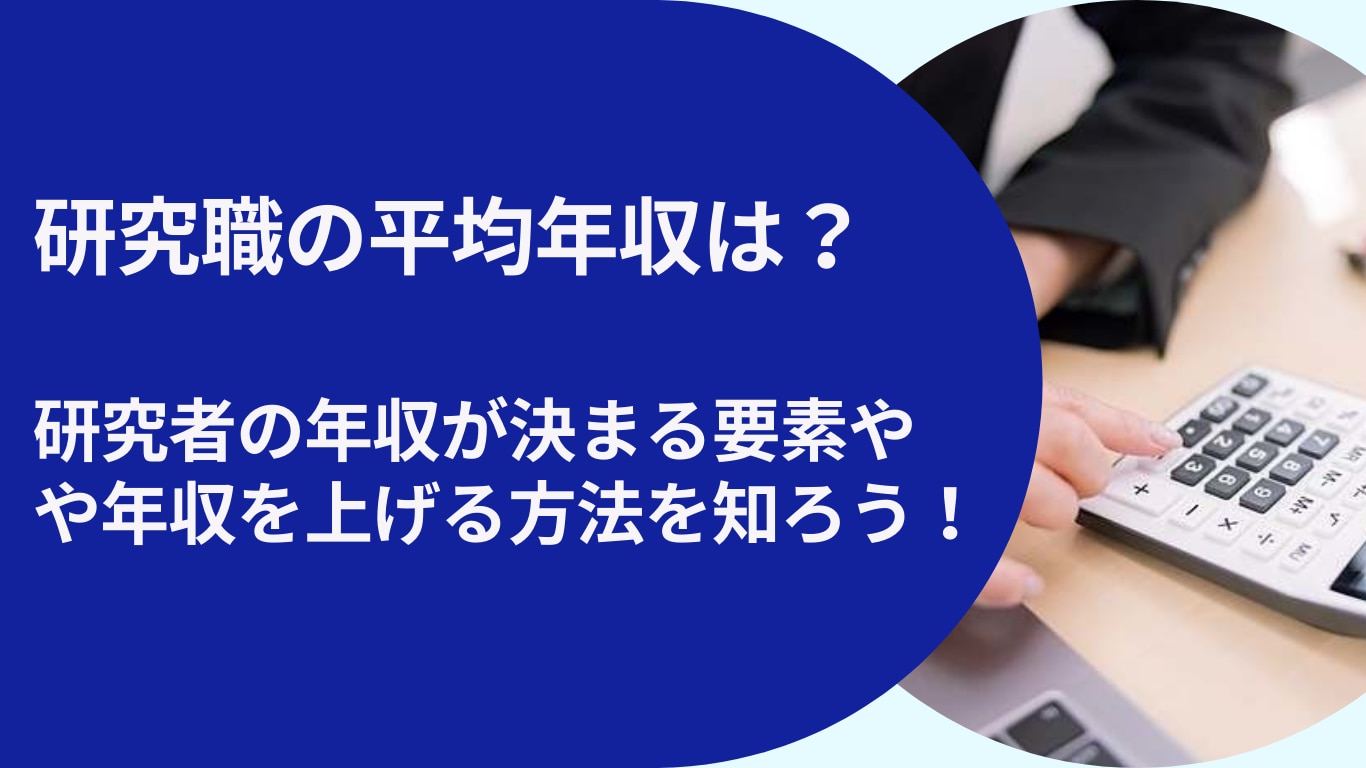
研究職の平均年収は?研究者の年収が決まる要素や上げる方法を解説!
「研究職の平均年収っていくらなの?」
「研究者の年収は何で決まっているの?」
「研究者として年収を上げるために何をすれば良いか知りたい」
このように、研究職の平均年収や給与額に疑問のある方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、研究職の平均年収や年収の内訳、年収を決定づける要素について紹介しています。
この記事を読むことで、研究職の平均年収や、年収がどのように決まっていくかを理解できるでしょう。
また、研究者の所属先別の平均年収や、年収を上げる方法も紹介しています。その内容をもとに、より年収の高い所属先を見つけ、自身の年収を上げるための活動が可能になります。
研究者の年収に疑問や不安のある方は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
目次[非表示]
- 1.研究職の平均年収は?
- 2.研究職の年収の構成要素
- 2.1.基本給・能力給
- 2.2.賞与・ボーナス
- 2.3.各種手当
- 2.4.研究費
- 2.5.副収入や副業
- 3.研究者の所属先ごとの平均年収
- 4.研究職の年収が決まる要素
- 4.1.専門分野
- 4.2.最終学歴
- 4.3.研究実績
- 4.4.語学力
- 5.研究者が年収を上げるには?
- 5.1.資格取得
- 5.2.海外で働く
- 5.3.条件の良い企業へ転職
- 6.研究職の年収が決まる仕組みは理解しておこう
研究職の平均年収は?
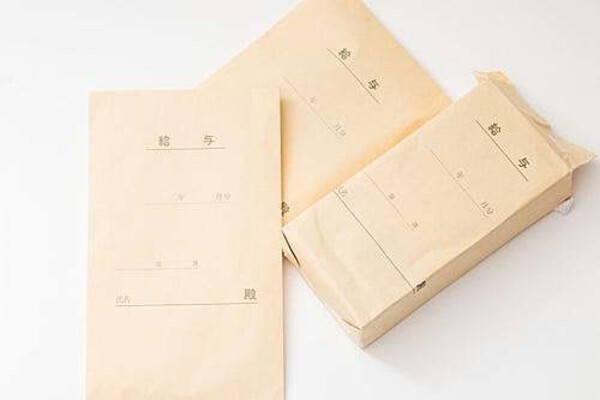
研究職の正社員の平均年収は、とある求人サイトの情報によれば約570万円で、月給換算すると約50万円になり、初任給は約20万円です。
ただし平均年収の結果だけを見ると、約380万円~1,000万円と大きく開きがあり、この差は研究者自身のスキルや、勤務先の違いなどによって生まれます。
また、正社員以外の給料に関しては、アルバイトやパートとして働いている方の時給が約1,200円、派遣社員の時給が約1,600円、という調査結果も出ています。
研究職の年収の構成要素

多くの職種で給与体系は「基準内賃金」と「基準外賃金」に分けられます。基準内賃金は所定労働時間内の労働に対する対価を指し、基準外賃金は所定労働時間にかかわらず支払われる賃金のことを指します。
研究職への給料でも、基準内賃金の基本給や基準外賃金の手当などが支払われています。
その他に、研究者ならではといった独自の報酬も存在するため、下記の内容をよく確認してみましょう。
基本給・能力給
研究職における「基本給」や「能力給」は、研究者自身の学歴や保有するスキル、年齢などによって変わってくる給与のことです。
例えば大卒で○万円といったように金額があらかじめ決まっているのが基本給で、研究成果を挙げた人に支払われるというものが能力給とされています。
基本給や能力給は、研究者としてキャリアを積み、研究成果を出し続けることで上げられるでしょう。
賞与・ボーナス
研究職は一般的な会社員と同様に、1年に2回「賞与」や「ボーナス」が支給されるでしょう。
研究職が1度の賞与やボーナスでもらえる額は、約40万円~50万円です。
ただし、勤め先の規模や制度、自社の直近6か月以内の業績などが影響するため、常に同額が支払われるとは限らないでしょう。働く部門や研究成果を挙げたか否かによって、賞与やボーナスの金額に差が出る可能性もあります。
各種手当
勤め先によっては、研究職に様々な手当が支払われる場合があります。
一般的な手当は以下の通りです。
- 通勤手当:自宅から勤務地に通うために公共交通機関などを使用している場合につく
- 住宅手当:賃貸等に居住している人につく
- 出張手当:普段の勤務地とは異なる場所へおもむき、業務にあたる際につく
- 時間外手当:時間外労働が発生した際につく
研究費
研究職には、年収以外に「研究費」が支払われる場合もあります。
研究費とは、研究者に与えられる研究のための予算のことです。研究に必要な書籍の購入や、実地調査を行うためなどに、この費用が用いられます。ただし、研究費は研究者の収入になる訳ではないため留意してください。
日本国内には、年間で100万円程の研究費がもらえる研究所も存在します。
副収入や副業
勤め先が副業を認めている企業であれば、研究者は副業により副収入を得ることが可能です。
研究者の副収入の例には、書籍の出版や監修、メディアへの出演やセミナー講演、ブログの公開などが挙げられます。
特に、自身が研究している分野の第一人者ともなれば、副収入を得られるチャンスが多数あるでしょう。
しかし、研究者の勤務先の中には、副業を認めていないところもあります。事前に副業可能かどうか、勤務先の規定をしっかり確認しておくことが大切です。
研究者の所属先ごとの平均年収

研究者は、所属先によって平均年収が変わってきます。
- 研究所:年俸制で600万円以上
- 民間企業:新卒で300万円~400万円
- 大学:800万円~1,000万円
また、どの研究所や民間企業に所属するか、所属大学が公立か私立かといった違いでも、平均年収は異なってくるでしょう。
研究職の年収が決まる要素

研究職の年収が決まる際には、いくつか考慮されるポイントがあります。
例えば、研究者が何を専門としているか、どのような学歴を持っているかは年収に影響を与えます。他に、研究者自身のスキルや、これまでに成してきたことも年収に反映されるでしょう。
研究者の年収を決定づけるポイントが知りたい方は、下記を参考にしてみてください。
専門分野
研究者の年収は、属する専門分野によって大きく変化します。
研究分野にはライフサイエンスや情報通信、ナノテクノロジーやエネルギー、社会基盤など様々あり、そこからさらに細かく分かれています。
多くの専門分野の中で、今後一層発展していくと考えられている分野は、化学系や薬学、バイオ系、ロボットやAIなどです。これらの分野での研究者へのニーズは高く、平均年収も高めに設定されているでしょう。
最終学歴
研究者は、「修士課程修了(修士号)」か「博士課程修了(博士号)」かといったことも、平均年収に影響します。
修士課程修了よりも、博士課程修了の方が平均年収は高くなるでしょう。例えば、修士課程修了の基本給が約20万円であれば、博士課程修了の基本給は約30万円といったようになります。
また、研究職の採用では、修士課程修了や博士課程修了を条件に設定されていることがあります。
研究実績
研究者が自身の研究で成果を挙げていれば、年収に影響を与えるでしょう。
研究者として実績を挙げるためにしておきたいことは、国内外の学会での発表や論文の投稿などです。特に論文誌への論文投稿は、研究者として客観的な評価を得るためや、博士号取得のために必要になります。
上記だけでなく、共同研究実績も重要です。他の企業や大学と共同研究をすることで、実際に研究に参加した実績ができます。また研究に参加した、他の組織の人とのコネクションを評価されることもあるでしょう。
語学力
語学力は研究者に必要なため、年収に反映される可能性があります。
研究者は国内だけでなく国外の研究者ともコミュニケーションを取ったり、海外の研究者が発表した論文を読んだりする機会があるためです。
時には研究者自身の論文を、英語で投稿する機会もあるでしょう。また、研究職への就職を目指す際にも、一定の語学力を求められる場合があります。
研究者が年収を上げるには?

研究職は研究している分野や修士と博士の違いなどで、年収の上がり方が変わりますが、それ以外にも年収を上げる方法はあります。
例えば、研究者自身がスキルを身につけたり、環境を変えたりすることで、年収がアップする可能性があるでしょう。
以下では、研究者が年収を上げるためにできることを紹介します。
資格取得
研究に役立つ資格や語学力を客観的に示すことで、年収を上げられます。
資格取得の候補になるのは、品質管理を徹底するための「品質管理検定(OC検定)」や、消防法で定められた危険物を取り扱うための「危険物取扱者」などです。
語学力については、TOEICのスコアなどで評価されます。
企業によっては、資格取得で資格手当が付くこともあるでしょう。
出典:TOEIC|一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
海外で働く
研究者の年収を高める方法には、日本よりも給与の高い海外で働く方法もあります。
これは、日本国内だけでなく国外の大学や企業でも優秀な研究者が求められており、日本よりも海外の方が、給与水準が高く設定されていることが理由です。
特に、欧米の大学と日本の大学との研究者の給与の格差は、徐々に広がってきていると言われています。
海外で働くためには語学力やコミュニケーション能力が求められますが、実現できれば高い年収を得られるでしょう。
条件の良い企業へ転職
研究者として長く勤め、研究成果を挙げていても待遇が改善しない場合は、より自身の実績を評価してくれる企業への転職を検討してみましょう。
大手製薬会社のように、研究費に多額の投資をしている企業では、研究者の給与も高水準で設定されている可能性が高くなります。しかし報酬が良い分、企業の方針や需要に沿った分野の研究をすることが求められます。
このため、自身の研究を好きに行いたい場合は、自由研究をする時間が確保された企業を目指すのがおすすめです。
例えば、Google社では、勤務時間の20%を好きなことに使って良い「20%ルール」を実施しています。20%ルールの活用によって従業員の創造力が育まれ、多くの新たなサービスが誕生した結果、企業の競争力を高めることに繋がっています。
出典:イノベーションが生まれる職場環境をつくる|グーグル合同会社
研究職の年収が決まる仕組みは理解しておこう

研究職の年収は、基本給や賞与だけでなく、資格手当や通勤手当などの手当で構成されています。その他に研究に使える研究費があり、勤務先が副業を許可していれば、副収入を得ることも可能です。
研究者の年収は、専門分野や修士か博士かといった学歴、これまでの実績などで決まりますが、勤務先によっても年収は変わってきます。
研究者が年収を上げたい場合は、資格の取得や、より待遇の良い企業や海外で働くことを目指すと良いでしょう。