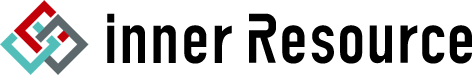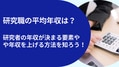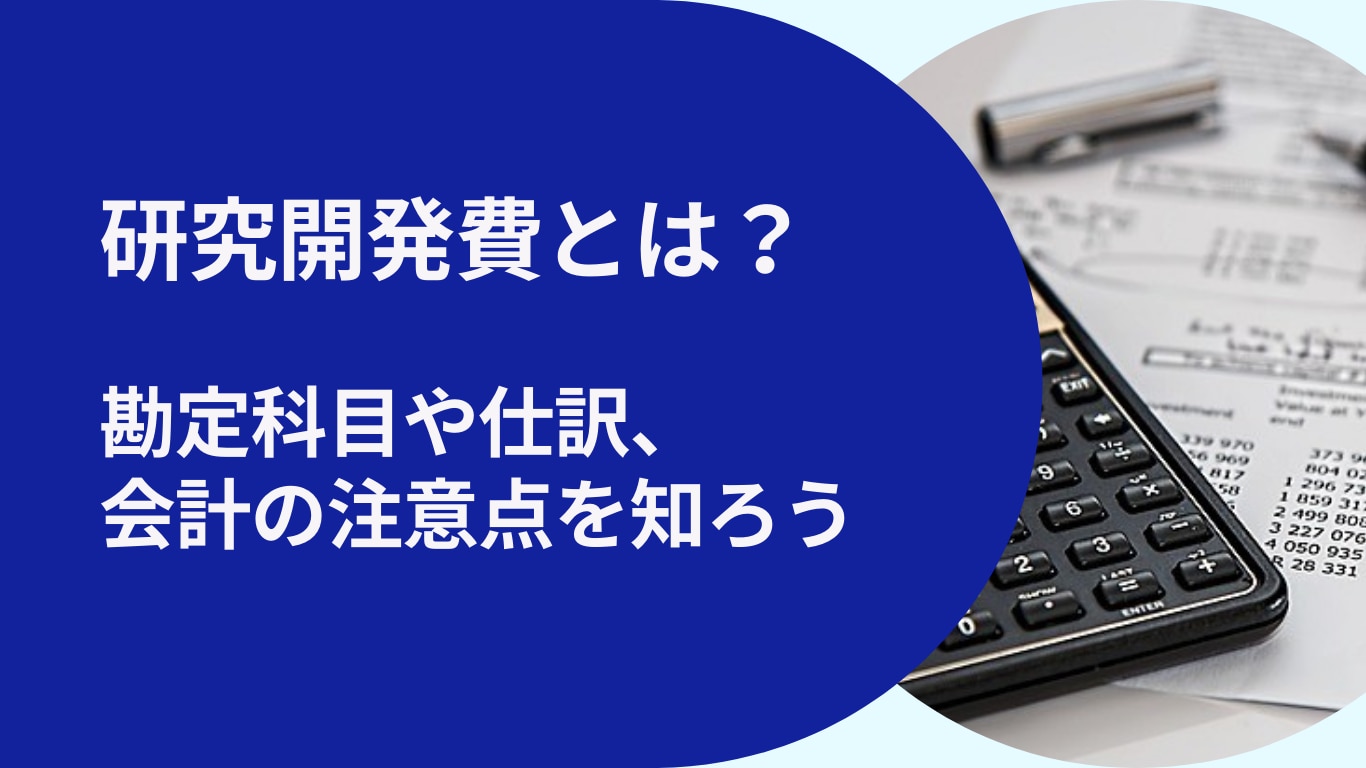
研究開発費とは?勘定科目や仕訳、計上できるケースや会計の注意点を解説
「研究開発費とは具体的に何を指しているの?」
「一般的な開発費と研究開発費の違いは何?」
「研究開発費を計上する時に使う勘定科目や仕訳例を知りたい」
新たな製品やサービスを作るには、まとまった時間と費用が必要です。
しかし研究開発にまつわる作業は多種多様で、複雑な会計処理にお悩みの方もいるでしょう。
本記事では研究開発費の概要と、どのような費用が計上できるのかを解説します。
あわせて計上時の注意点や、研究開発の主な作業に使われる勘定科目と仕訳例も紹介します。この記事を読むことで研究開発費とは何かが分かり、スムーズな会計処理ができるようになるでしょう。
研究開発費の概要を知りたい方、費用計上のタイミングや具体的な仕訳例をお探しの会計担当者の方は、本記事をチェックしてください。
目次[非表示]
- 1.研究開発費とは
- 2.研究開発費と開発費の違い
- 3.研究開発費として計上できる費用
- 4.研究開発費として計上できない費用
- 5.研究開発費の会計時の注意点
- 5.1.研究開発費は発生したタイミングで計上する
- 5.2.外部委託した場合では処理が異なる
- 6.研究開発費の勘定科目と仕訳例
- 6.1.研究目的で機械設備を購入した場合
- 6.2.外部委託先へ支払いをした場合
- 6.3.販売目的のソフトウェアを開発した場合
- 7.研究開発費を理解して正しく会計を行おう
研究開発費とは

研究開発費とは新しい技術や製品の開発、または改良のために実施する市場調査や実験、設備導入の費用を計上する勘定科目です。
主なものとして、プロジェクトメンバーの労務費や設備費、原材料の購入費などが挙げられます。
研究開発費は主に、新たなものを生み出すための計画的な研究や実験で発生するものと、既存の製品を改良する際の費用に分けられることを覚えておきましょう。
研究開発費と開発費の違い

研究開発費と開発費は混同されることが多い言葉ですが、費用を計上するタイミングが異なります。
研究開発費は発生時に処理するのが原則です。一般的に、設備や原材料の購入費、調査費用や労務費などは、発生時に費用計上を行う必要があります。
一方、かけた費用の効果が翌年以降にわたって続くものが開発費です。このような費用は「繰延資産」と呼ばれ、支出後から数年間の定められた期間にわたって償却します。
研究開発費として計上できる費用

会計処理時には、その費用が研究開発費として計上できるのかを把握しておくことが大切です。
日本公認会計士協会の資料によれば、以下の9項目が研究開発の範囲として挙げられていることが分かります。新製品やサービスの開発だけでなく、既存のものに対する新たな使用方法を見つけることも、研究開発の範囲に含まれています。
- 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
- 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
- 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
- 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
- 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
- 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
- 新製品の試作品の設計・製作及び実験
- 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
- 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動
出典:研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針|日本公認会計士協会
研究開発費として計上できない費用

研究活動の中には、研究開発費として計上できない作業や物品があることに注意しましょう。
研究開発費として認められているのは、新たな製品やサービスを生み出すための活動や物品購入、労務費などです。
従来製品やサービスの量産化にかかる活動や、仕様変更などの軽微な改善は著しい変更とは言えず、研究開発費として計上できません。
日本公認会計士協会による具体例は以下の通りです。
- 製品を量産化するための試作
- 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
- 仕損品の手直し、再加工など
- 製品の品質改良、製造工程における改善活動
- 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
- 客先の要望等による設計変更や仕様変更
- 通常の製造工程の維持活動
- 機械設備の移転や製造ラインの変更
- 特許権や実用新案権の出願などの費用
- 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動
出典:研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針|日本公認会計士協会
研究開発費の会計時の注意点

会計処理では勘定科目や計上日などにルールが存在します。
特に研究開発費においては、作業内容や誰が担当したのかによって、計上タイミングや計上方法が変わることに注意が必要です。
ここからは、研究開発費を会計処理する際の主な注意点を2つ紹介します。
研究開発費は発生したタイミングで計上する
研究開発費は、原則として発生したタイミングで費用計上を行います。
労務費や研究に必要な原材料や消耗品費、研究施設など固定資産の減価償却費が対象です。発生時以外のタイミングでは計上できないことを覚えておきましょう。
研究開発費の対象になるのか迷った時には、製品やサービスに直接関連する費用かどうかを見きわめ、会計基準に沿って対応することをおすすめします。
外部委託した場合では処理が異なる
研究開発にまつわる作業を外部業者に委託した場合は、会計処理が異なることに注意しましょう。
例えば新製品やサービス開発前の市場調査や、研究に必要なソフトウェア開発の発注などは研究開発業務では珍しくありません。このような外部委託にかかる費用は、業者から成果物を受け取り、自社で検収した時点で会計計上を行います。
外部業者にあらかじめ費用の一部を支払っている場合は、検収のタイミングでその費用計上を取り消し、研究開発費として再計上することにも注意が必要です。
研究開発費の勘定科目と仕訳例
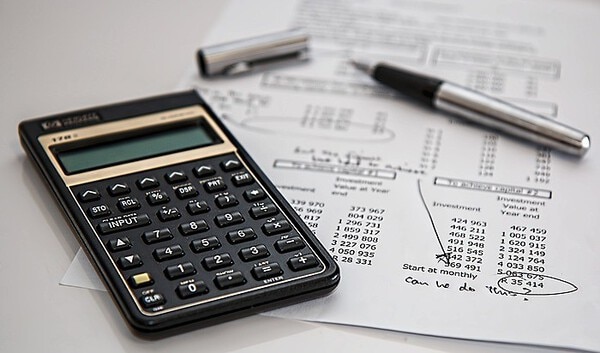
研究開発費の会計処理では、発生した作業や費用によって、使用する勘定科目や仕訳方法が決まっています。
計上方法を誤ると研究開発にかかった費用を把握できなくなり、企業の損益にも影響を与えることになりかねません。
ここからは、研究開発でよく発生する3種類の費用について、具体的な勘定科目と仕訳の例を紹介します。
研究目的で機械設備を購入した場合
製品開発に必要な実験や研究に使用する機械設備を購入した場合は、購入時に費用を計上します。
購入した機械を資産として扱う場合は、資産計上後に減価償却の処理を実施してください。
新製品開発用の実験装置を800,000円で購入し、普通預金から支払った場合の仕訳例(資産計上しない場合)を下記で紹介します。
| 借方 | 貸方 |
適用 |
研究開発費 800,000円 |
普通預金 800,000円 |
新製品開発のため実験装置を購入 |
外部委託先へ支払いをした場合
新製品やサービスの開発前に市場のニーズを把握することも、研究開発作業の一つです。
このような調査は専門業者に委託して行われることが多く、かかった費用は研究開発費として計上できます。
新製品の市場開拓を目的としてマーケティング会社に調査を依頼し、代金250,000円を現金で支払った場合の仕訳例は以下の通りです。
借方 |
貸方 |
適用 |
研究開発費 250,000円 |
普通預金 250,000円 |
市場調査代金 |
販売目的のソフトウェアを開発した場合
販売を目的としたソフトウェア開発においては、原則として企画の段階から費用計上を行います。製品化したものは資産計上が認められますが、それ以前に発生した費用は研究開発費となる点に注意が必要です。
販売目的のソフトウェア開発にかかった事前調査、開発ツール購入、プログラム開発に12,000,000円を支出した場合の仕訳例を以下に記載します。支出項目が複数にわたるため、貸方科目の未払金は、現金や預金などを使用してもかまいません。
借方 |
貸方 |
適用 |
研究開発費 12,000,000円
|
未払金 12,000,000 円 |
ソフトウェア開発費用 |
研究開発費を理解して正しく会計を行おう

研究開発費とは何か、開発費との違いや計上対象となる費用、会計処理のタイミングや注意点と具体的な仕訳例を紹介しました。
新しい製品やサービスを生み出すには様々な事前調査や備品購入の他、まとまった時間をかけた取り組みが必要です。
どのような費用が研究開発費になるのか、計上タイミングや仕訳方法を理解することで、迷わずに会計処理を進められるようになるでしょう。
複雑な研究開発費用の内容を整理し、適切な会計処理ができるように知識を増やすことを心がけてください。