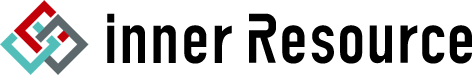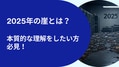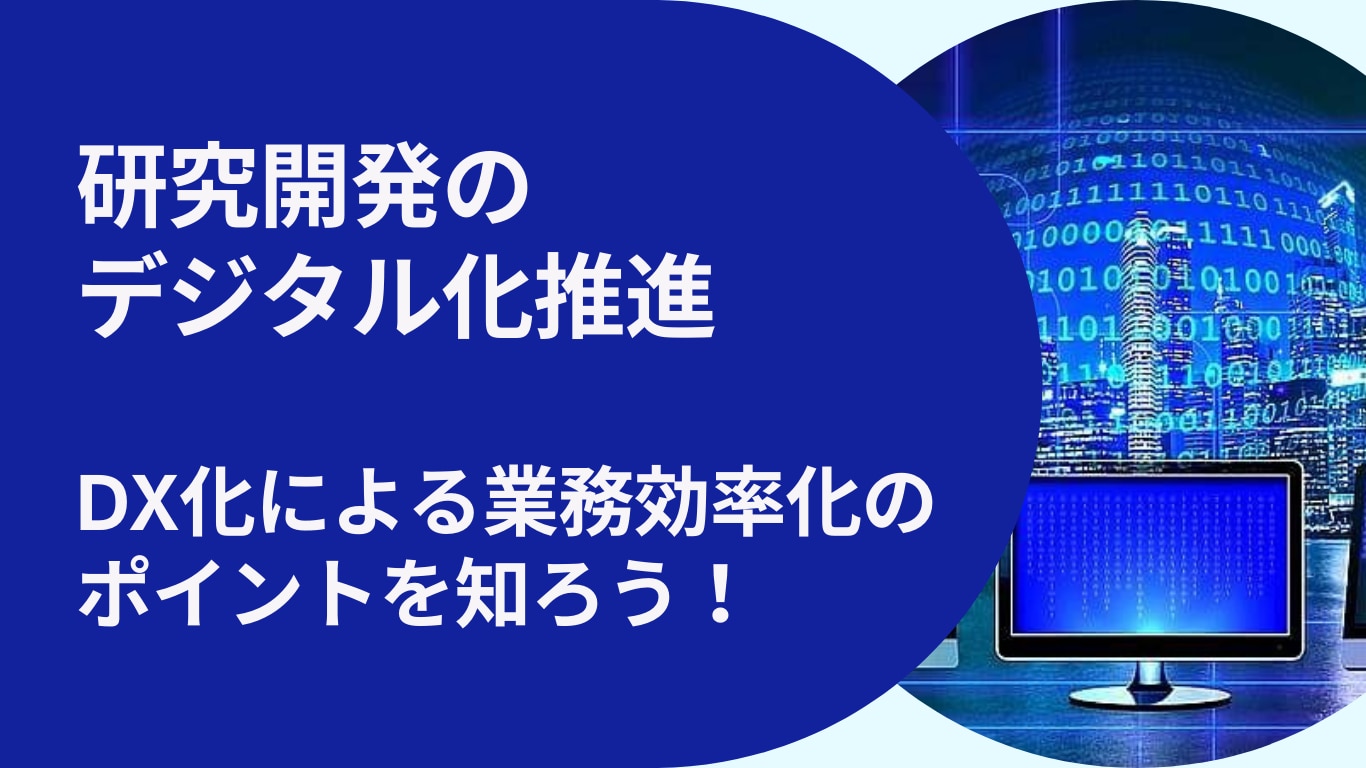
研究開発のデジタル化推進とDX化による業務効率化のポイント
「DXという言葉は聞くけれど、具体的な内容がわからない」
「IT化とDX化は何が違うの?」
「DXを使って研究開発の業務効率化を行いたい」
IT業界に限らず、様々な分野でDX化の動きが活発になっています。しかし、どのようにDX化を進めれば良いのかわからずお悩みの方もいるでしょう。
本記事ではDXの基礎知識と、国の政策に掲げられているデジタル化推進プランの解説に加え、DX化によって研究開発業務を効率化するためのポイントも紹介しています。
この記事を読むことでDXとは何かがわかり、効率的に研究開発業務を行えるようになるでしょう。
DXについて詳しく知りたい方、研究開発業務のDX化に必要な知識や推進方法を知りたい方は、本記事をチェックしてください。
目次[非表示]
- 1.DXとは
- 2.研究開発のデジタル化推進プラン
- 2.1.デジタル社会への最先端技術・研究基盤の活用
- 2.2.将来のデジタル社会に向けた基幹技術の研究開発
- 2.3.研究環境のデジタル化の推進
- 3.DX化による研究開発の業務効率化のポイント
- 3.1.データの一元管理
- 3.2.各種手続きのデジタル化
- 3.3.支援ツールの活用
- 3.4.最新技術の活用
- 3.5.DX人材の育成と確保
- 4.DX化によって研究開発の業務を効率化しよう
DXとは

DXは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語で、「デジタル技術を使って社会や生活を変革すること」です。
企業においては、急速なビジネス環境の変化に対応するために、IoT(Internet of Things:ものインターネット)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)などのIT技術を使って製品やサービス、業務プロセスを改善することを指します。
デジタル技術を導入して品質を向上できるだけでなく、自社の業務のやり方や効率化もDXで実現可能です。
研究開発のデジタル化推進プラン

DXによって社会の様々な分野の効率化が期待されており、研究開発分野もその中の一つです。
研究開発は企業が製品やサービスを生み出すために必要なものですが、どのように推進すれば良いのかわかりにくいと感じたこともあるでしょう。
ここからは、2020年に文部科学省が発表した「文部科学省におけるデジタル化推進プラン」に挙げられている3つのプランを紹介します。
出典:文部科学省におけるデジタル化推進プラン|文部科学省デジタル化推進本部
デジタル社会への最先端技術・研究基盤の活用
最新の設備や技術を導入し、デジタル社会に対応する環境を整えることが、一つめの施策です。
スーパーコンピュータやインフラを整備し、ビッグデータと呼ばれる様々な情報をデータベース化して研究に使えるようにすることが掲げられています。
また、各研究機関で情報を共有できる体制を作り、国内全体での研究開発の効率化やレベルアップも施策の一つです。
このような動きは「データ駆動型研究」と呼ばれます。これは事前に仮説を立てず大量のデータを集め、分析した上で研究を進めるという意味があり、世界の研究では主流になっています。
将来のデジタル社会に向けた基幹技術の研究開発
次に、研究に必要な基幹技術の開発が推進プランとして挙げられます。
次世代の技術として注目されているロボットや量子技術、環境エネルギー分野に投資し、世界での産業競争力を高めるのがねらいです。
また、AI技術の高度化を目指し、公平性・透明性・説明性を持つ高度なAI技術の導入も戦略に掲げられています。
基幹技術の導入により国と民間団体が協力して研究開発力を向上させ、成果創出の加速化につながることが期待できます。
研究環境のデジタル化の推進
研究開発を行う環境のデジタル化も、重要な施策の一つです。
これを「研究DX」と呼び、オープンサイエンス時代を先導して、ワンストップで行える研究環境のデジタル化を目指しています。その課題として、国と研究機関の連携によるノウハウの共有や研究に必要なツールの導入、研究における遠隔操作や自動化させることが挙がりました。
上記の他、国際競争で勝ち抜くためのDX人材の育成や確保の取り組みも行われています。
DX化による研究開発の業務効率化のポイント

研究開発業務を効率化する必要性があると感じているが、具体的な進め方や導入するツールなどがわからずお困りの方もいるでしょう。DX化により業務を効率化するためには、いくつかのポイントがあります。
ここからは、業務効率化を推進するための主なポイントを5つに分けて紹介します。
データの一元管理
まずは、研究開発で使うデータの一元管理から始めましょう。
研究活動においては調査資料や実験結果など様々なデータを扱うことが多く、保管場所が多岐にわたることもあります。また、作業の属人化によってデータやノウハウの継承が困難になる場合もあるでしょう。
これらを解決する策が、DX化によるデータの一元管理です。関係者がいつでも場所を選ばずに使えるようにすることで、作業の効率化に加えてナレッジのスムーズな共有にも効果を発揮します。
各種手続きのデジタル化
手続きに伴う作業のデジタル化も、業務効率化に有効です。
研究活動では実験などの作業データだけでなく、研究所内や各機関への申請書類も多数発生します。研究者がこれらの作業に追われた際、本来の研究活動に十分な時間をかけられず、支障をきたすこととなります。
その改善策として、業務フローや事務作業を見直しデジタル技術を活用すれば、円滑な研究活動が期待できるでしょう。
支援ツールの活用
研究活動の効率化には、支援ツールの活用も有効です。
例えば、設計や解析用のツールを導入することで、これまで手作業で行っていたシミュレーションやCAD(Computer Aided Design:コンピュータ支援設計)のモデリングを効率的に行えるようになります。
さらに、研究プロジェクトの管理や、生産・販売部門との連携ができるツールを併用すれば、関係各所との情報共有がスムーズになるでしょう。
また、研究活動だけでなく、開発した製品やサービスのライフサイクルなども支援できるツールを活用することで、研究の品質やスピードが上がる効果も期待できます。
最新技術の活用
最新のデジタル技術を活用することも、研究開発業務の効率化に役立ちます。
研究開発では様々な設計や実験を行いますが、最新の技術を導入することで高精度な作業を短時間で実施できるだけでなく、うまく活用することで残業代などのコスト削減も可能です。
例えば模型などの試作工程ではまず金型を準備し、粘土や樹脂などを使って手作業で作成していました。しかし、3Dプリンターを使うと金型が不要で、複雑な造形物も比較的容易に作成できます。
他にもロボットを使った実験の自動化や、スマートグラスやパワーアシストスーツといった人間の能力を補完する「人間拡張」と呼ばれる技術の導入も注目を集めています。
DX人材の育成と確保
最新のデジタル技術を活用することも、研究開発業務の効率化に役立ちます。
業務効率化においては、設備や技術だけでなく「DX人材」を確保し、育てることも重要なポイントです。
IT化の機運が高まった頃に導入したシステムを使いこなせず、業務を改善できていないという事例も少なくありません。
最新のITやデジタルのスキルを持ち、DXを推進するのに必要な知見や考え方を持つDX人材がデジタル化を主導していくことで、DX化が進むと言われています。
DX人材は不足傾向にあるため、新卒採用や在籍する社員の育成も必要です。社内システムや業務フローに詳しい社員にDXスキルを持たせることで、業務効率化をスムーズに進められるでしょう。
DX化によって研究開発の業務を効率化しよう

DXとは何か、国が進めるデジタル化推進プランの概要と、DXを用いて研究開発の効率化を行う際のポイントを紹介しました。
デジタル技術は身近になりましたが、研究開発においては膨大な時間と手間をかけて作業しているのが実情です。
DX化によって研究者の負担を軽減するだけでなく、品質向上や様々なコスト削減にもつながることが期待されています。
DX化には高いデジタルスキルを持ち、長期的な視点でDXを推進できる人材を確保することも欠かせません。より高度な研究開発を進めるために国や業界の動向をチェックし、業務の効率化に取り組んでみてください。